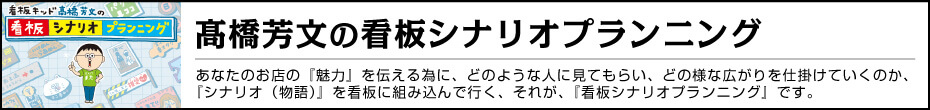第四回目。いまや東京を代表するランドマークとなった巨大なサイン「I LOVE 歌舞伎町」など、これまでにないエンタメ看板の仕掛人として活躍する“看板キッド”こと高橋芳文さんに、看板ウオッチャーとしても知られる放送作家の吉村智樹が迫ります。

今回はその第四回目。
2015年4月1日エイプリルフールに野方の商店街で実施された「人がクスッとするジョークの張り紙プロジェクト」についておうかがいしました。
――高橋さんの大きな功績のひとつに2015年4月1日のエイプリルフールに野方の商店街で開かれた「人がクスッとするジョークの張り紙プロジェクト」がありますね。さまざまなメディアが報じたこの催しは、どのようないきさつで始まったのでしょうか。
僕はもともと「ストリートデザイン研究機構」っていうNPO法人をたちあげて理事長をやってたんです。いまは3代目に譲っているんですけれど。その関係でうちの本拠地である中野区の街おこしにかかわっていたんです。それで僕が「エイプリルフールにみんなでウソの看板を出したらおもしろいんじゃないか」と提案したんです。
――ネットでは企業のエイプリルフール広告を見たことがあったんですが、商店街まるごと軒先にウソを貼りだすって、思い切った計画ですね。
「ウソをつくコミュニケーション」というツールをつくってみたかった。野方という下町であることと「町ぐるみでジョーク」「みんなでウソをつく」という点が重要だったんです。くだらないセンスの店が一軒だけだとヒかれちゃうけど、いっぱい集まると笑える感覚って、あるじゃないですか。
――どの店もどの店も書いてあることがおかしい、っておもしろいですね。どのような様子だったのですか?
店主自らが書いたジョークをそれぞれ窓ガラスに貼りだしました。「A4サイズで同じ紙のフォーマット」というレギュレーションだけがあって、あとは皆さんマジックなどを使い、手書きで自由に。へたうま関係なく。かかるお金は紙代とインク代だけ。
――街がジョークギャラリーになったんですね。それは壮観です。どのような作品が貼りだされたのですか?
プリントショップなら「本日、日本銀行券印刷賜わります」、居酒屋なら「あつあつの生ビールあります」、文具店は「デスノート販売中」、メガネ屋さんは「透視メガネ販売中」、ガラス製品の店は「鏡割り放題」、不動産屋さんは「座敷わらしつき物件出ました」、お蕎麦屋は「当店使用の粉は末端価格で〇〇〇万円」、コンビニだったら「24時間営業やめました」、などなど、たくさんの店が参画してくれました。
――どの貼り紙もジョークが効いていますね。イベントタイトル通り「クスッ」としてしまいます。コンビニの貼り紙はこのご時世、ウソかどうか判断しがたいギリギリですが……。そしてこの催しは多くのメディアに採りあげられましたね。
新聞は「東京新聞」夕刊の1面、テレビは「J-COM」、ネットは「Yahoo! 二ュース」や「中野経済新聞」、ほか、あらゆる媒体に掲載されました。取材の依頼が殺到したため榎本理事長がNHKはことわっちゃったくらいです。
――自分たちでも宣伝をされたんですか?
いいえ、売りこみや宣伝はほとんどしていないし、当日もマップなど案内の販促物をつくらなかったから、どこになにがあるのかもわからない。どの店がどんな情報を掲げているのかわかんないわけです。知ろうと思えば商店街をさまようしかない。そういうイベントがここまで世間に広まったのはやはりSNSでした。「野方でジョークの貼り紙をやってる」って誰かが撮影してTwitterにアップしたら、みるみる拡散したんです。ほんとうにくだらない、B級な言葉を貼りだすことで、街の人たちが足を留める。スマホなどで撮影してSNSにアップする。格好の「投稿ネタ」なんです。そしてそれを見た人がシェアし、さらに自分も投稿したいからって、わざわざ撮りにやってくる。そういう相乗効果的な動きがありました。
 ――Yahoo! 二ュースにいたっては開催時間内に報道されたんだそうですね。
――Yahoo! 二ュースにいたっては開催時間内に報道されたんだそうですね。
そんときに榎本理事長が言ったセリフが効いたんですよ。「キワドイものは現地へ見に行け!」ってね。正直、アブなくてYahoo! 二ュースには載せられないような貼り紙もあったんです。だから現地へ行って自分の目で確かめるしかない。そうやってネットユーザーを煽ったおかげで、よりいっそう、どんどんどんどん拡散して。
――予算はほとんどかからないし、経済効果は抜群ですね。
商店街って日ごろは地元の人だけが利用するじゃないですか。それがSNSでシェアされたことで街の外から人がどんどん来たんです。そして街全体でやっているから、くまなく歩かないと把握できない。そうやって歩きながら滞在しているうちに、訪れた人たちは商店街でお金を使っていきますよね。テレビや新聞などのマス広告がむかしほど効かなくなったと言われる昨今、A4サイズの言葉を街ぐるみでおもしろがるだけ、しかもパソコンなんて使わないで、こんなににぎわったんです。このようにソーシャルメディアとアナログな看板は相性がいいんですよ。それに経済効果だけではなく、榎本理事長曰く「お客さんとお店の人が触れあったことで、イベントのあと、街の雰囲気が明るくなった」のだそうです。このツールはこれから、ちょっとさびれた街などにも応用できるでしょう。
――手書きの貼り紙というアナログな表現だからこそデジタルの時代に映えたんですね。それにしても皆さん、言葉のチョイスや書き方がお上手ですね。制作方法をお教えになられたのですか?
ワークショップはしましたね。僕は自分で看板を企画するときも、まずシナリオを考えるんです。僕は「看板シナリオプランナー」を名乗っているんです。この看板にはどういう物語があるか、というね。そう考えることで看板に味が出てくる。そういう話をしました。あとは手書きのよさを説きました。へたでいいんです。へたなくらいの書体だと逆に見てもらえるじゃないですか。お店の話題づくり、ひいてはお店の認知促進に効果を発揮するでしょう。パソコンで作るとうまくはなるんですけれど味がなくなっちゃうんで。だから「徹底的にアナログで」と伝えました。
――それで皆さん、味わい深い表現になったのですね。しかしながら、看板のプロが看板づくりのノウハウをやすやすと一般の方に伝授してしまってよいのでしょうか。看板キッド自ら手の内を見せすぎているのではと心配になってしまいます。
いえ、僕らの会社は「看板に愛、人に笑顔、まちに幸せを」がモットーで、看板をつくりさえすればいいとは考えていない。看板を愛して人に笑顔を届けて街を幸せにしていくのが仕事です。地域の人たちが集まっているところで「こうしたほうがいいんじゃないか」と伝て、そのなかで「やってみよう」と思ってくれる人がいたら、少しは役に立てたかなって思えますね。
 ――とはいえ看板って、素人につくれるものなんでしょうか?
――とはいえ看板って、素人につくれるものなんでしょうか?
プロにしかつくれない看板は、もちろんあります。それは僕たちにお任せください。しかし逆にプロでは表現できない店主の味だったり、あるいは「子供にしかつくれない看板」ってあると思うんです。子供が看板を描いたっていいし、子供と大人が共同でつくってもいい。看板がキットになっていて、子供でも小学校の工作の時間に組み立てられて、その組み立てた看板を商店街のおじさんにあげるとか、そんなことをしたいんですよ。それって広告的なプロっぽさが微塵もなく、世代を超えた地域のコミュニケーションになっているじゃないですか。僕は遊びのセミプロを名乗っていて、遊びながらものをつくる楽しさを伝えたい。手を動かし、指を使って遊んでいくとみんな楽しくて笑顔になってゆく。廃材や不用品、余っている地域資源だけで看板をつくるとかね。看板のつくりかたをどんどんかえてゆきたい。機械に頼らない、ハンドメイドで、アナログなかたちで看板を作っていくってのって楽しいでしょう。看板が人を楽しくさせ、コミュニケーションツールになっていく。それこそ僕が言う「看板に愛、人に笑顔、まちに幸せを」なんです。
――お話をうかがっていますと、これまで最先端を目指していた看板が、いま立ち止って原点へと還ろうとする転換期にあるように感じました。
あー、そうですね。1997年くらいまでは、看板は出せばお客が入っていたんです。まだインターネットが台頭する前で、お店を探す第一の方法が看板でしたし、問い合わせ方法は電話しかなかった。NTTのタウンページの広告費が、たしか当時は1800憶くらいあったんです。ところが1997年に「ぐるなび」が出始め、そのあと「食べログ」が出てきて、お店さがしの主流はインターネットになった。インターネットの台頭のおかげで2013年になったらタウンページの広告費は600億くらいまでさがっちゃったんですよね 三分の一に。さらにインクジェットプリンタの発達で、誰でも簡単にコンピュータで看板をつくれるようになった。看板を取り巻く状況は、このようにどんどんどんどんデジタル化していったんです。
――看板にあった人間くささが次第に消えていったんでしょうか。
そうですね。きれいでなんだけど、つまらない。でもそういう状況さえも飽和して、いまは人々がヘタでもアナログなものを求めはじめています。SNSの投稿って、ほとんどそうじゃないですか。だから僕は「くずしていこう」「プロっぽさを消していこう」「ヘンな方向へ振り切ろう」「VOWの要素をにじませよう」と言っているんです。“言葉の露出狂”を名乗りながら、猥雑で味のある言葉や表現に反応していきたい。
――一貫しておっしゃっていることの意味が、いっそうはっきりしました。
現存する世界最古の看板をご存知ですか?
――一いいえ、知らないです。
トルコのエフェソスに遺っている石に彫ってある看板なんですけど、「娼婦の館 こちら」と書かれているんです。看板の原点であり、僕が考えるプロっぽさを消した究極のかたちです。看板は、この原点へと還ってゆくのでしょう。
――ありがとうございました。
取材・執筆 吉村智樹(放送作家)